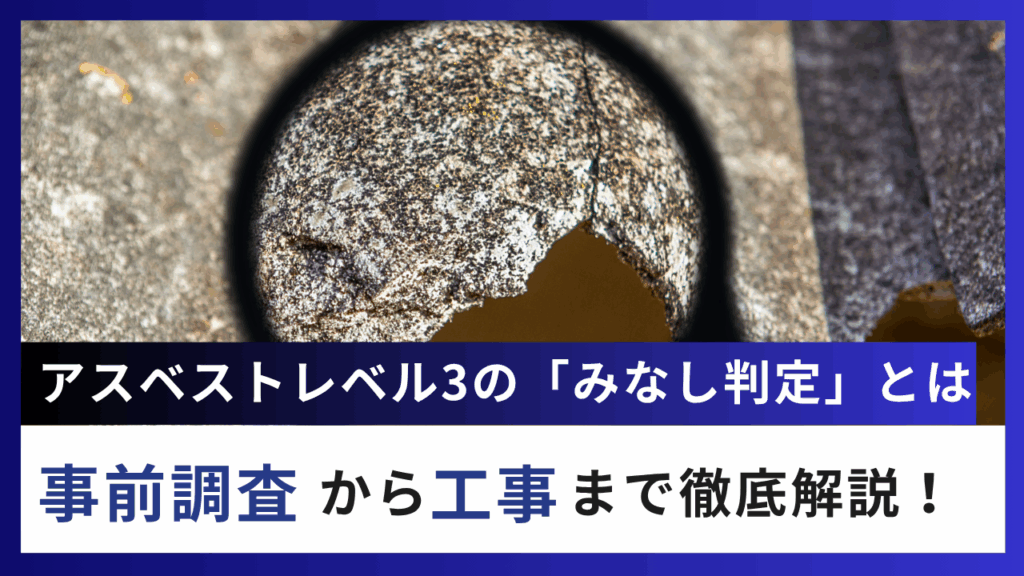建築物の解体や改修工事において、アスベスト(石綿)の存在は作業者や周辺環境に深刻な健康リスクをもたらします。アスベストは飛散性の高さに基づきレベル1からレベル3に分類され、それぞれに適切な対策が法的に義務付けられています。本記事では、最も飛散性が低いとされる「レベル3」のアスベストに焦点を当て、「みなし判定」の仕組み、事前調査、届出の要否について、公的機関の情報を基に専門的な視点から詳しく解説します。これにより、アスベストレベル3に関する正確な知識を習得し、安全かつ法令を遵守した工事計画の策定に役立つ具体的な指針を提供します。
アスベストの基礎知識とレベル分類:飛散性に応じたリスク理解
アスベスト対策には、その基本的な性質とリスクレベルの正確な理解が不可欠です。ここでは、アスベストの定義、危険性、そして飛散性に基づくレベル分類について解説します。
アスベストとは何か?その危険性と健康被害
アスベストは、天然に産出される繊維状ケイ酸塩鉱物の総称です。かつては耐熱性、耐摩擦性、耐酸性、耐アルカリ性、耐久性に優れる特性から、建材をはじめとする多様な工業製品に広く利用されました。しかし、その極めて微細な繊維を吸入すると、肺がん、中皮腫、石綿肺といった重篤な健康被害を引き起こすことが判明しています。これらの疾患は、アスベスト吸入から数十年という長い潜伏期間を経て発症することが多く、治療が困難であるため「静かな時限爆弾」とも称されます。日本では2006年にアスベストの製造・使用が原則禁止されましたが、既存建築物には依然としてアスベスト含有建材が残存しており、解体・改修工事における飛散防止対策は極めて重要です。
アスベストのレベル分類(レベル1, 2, 3)と各特徴
アスベスト含有建材は、解体・改修作業時の発じん性(粉じんの発生しやすさ)に応じて、レベル1からレベル3の3段階に分類されます。この分類は、作業の危険度を判断し、適切な飛散防止措置を講じるための重要な指標です。
・ レベル1:発じん性が著しく高い 石綿含有吹付け材などが該当し、最も厳重な管理と対策が求められます。
・ レベル2:発じん性が高い 石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などが該当し、レベル1に準じた飛散防止対策が必要です。
・ レベル3:発じん性が比較的低い 主に石綿含有成形板などの固い板状の製品が該当します。通常の状態では飛散リスクは低いですが、切断や破砕などの作業時には注意が必要です。
レベル3アスベスト建材の具体例と飛散性の特徴
レベル3に分類されるアスベスト建材は、セメントや樹脂などで固められた非飛散性のものがほとんどです。国土交通省の資料によると、具体的な建材としては、スレートボード、スレート波板、けい酸カルシウム板第1種、パーライト板、せっこうボード、ビニル床タイル、セメント円筒などが挙げられます。
これらの建材は、建築物の屋根、天井、壁、床など、様々な場所で使用されます。固形で安定しているため、原形のまま手作業で丁寧に取り外す場合は、粉じんの飛散リスクは比較的低いとされます。しかし、電動工具による切断や破砕、穿孔(穴開け)、研磨といった作業を行うと、固められていたアスベスト繊維が飛散し、作業場所の石綿濃度が高まる危険性があります。そのため、レベル3であっても、作業内容によっては湿潤化などの飛散防止措置や、適切な防じんマスクの着用が不可欠です。原形のまま取り外す場合は隔離養生は不要ですが、切断等が必要な場合は、状況に応じて隔離養生や湿潤化が求められます。
アスベストレベル3における「みなし判定」の全貌
アスベスト含有の有無を判断する際、「みなし判定」という選択肢が存在します。特にレベル3建材において検討されることが多いこの手法について、その定義からメリット・デメリットまでを詳しく解説します。
「みなし判定」とは?その定義と適用範囲
「みなし判定」とは、建材にアスベストが含まれているか否かを分析調査によって確定させることなく、「アスベストを含有しているものとみなして」扱う手法です。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」においても、アスベスト含有の有無を判断する方法の一つとして位置づけられています。この判定は、実際にはアスベストが含まれていない建材であっても、含有しているという前提で、法規制に則った除去・処理作業を行うことを意味します。みなし判定は、レベル3建材だけでなく、レベル2建材においても適用が認められています。
レベル3アスベストで「みなし判定」が可能な理由
レベル3建材でみなし判定が選択肢となる背景には、その特性が関係しています。レベル3に該当する石綿含有成形板などは、製品の裏面やロット番号、JIS規格番号、メーカー名といった情報から、アスベスト含有の有無をある程度推測することが可能です。しかし、情報が不明確であったり、データベースで確認できない場合も少なくありません。そのような状況で、分析調査にかかる時間や費用を考慮し、発注者の合意のもと、分析を省略して「みなし判定」を選択することがあります。
「みなし判定」のメリットとデメリット:コストとリスクのバランス
みなし判定を選択するかどうかは、コスト、工期、リスクを総合的に勘案して慎重に判断する必要があります。最大のメリットは、分析調査にかかる費用と時間を削減できる可能性がある点です。特に、アスベスト含有の可能性が極めて高いと判断される場合や、工事のスケジュールが非常にタイトな場合には有効な選択肢となり得ます。
一方で、デメリットも存在します。環境省の指針によれば、みなし判定を行った場合、「必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい石綿(アスベスト)対策措置を講じなければならない」とされています。これは、例えばレベル3建材であっても、アスベストの中でも特に危険性が高いとされるクロシドライト(青石綿)が含まれていると仮定し、レベル1に準拠した最高レベルの対策が求められる可能性があることを意味します。結果として、分析調査費用を節約した以上に、除去作業にかかる人件費や設備費が増大し、工期も延長され、トータルコストが割高になるケースも少なくありません。そのため、みなし判定を選択する際は、これらの潜在的なコスト増のリスクを発注者に十分に説明し、理解を得ることが不可欠です。
アスベスト事前調査の義務とレベル3における報告・届出
2022年4月1日から、建築物の解体・改修工事におけるアスベストの飛散防止対策が強化され、事前調査とその結果報告が厳格に義務付けられました。これはレベル3建材も例外ではありません。
アスベスト事前調査の法的義務と調査対象
大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づき、建築物や工作物の解体・改修作業を行う際には、アスベストの使用の有無を事前に調査することが事業者に義務付けられています。2023年10月からは、この事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの専門資格を持つ者が行う必要があります。調査は、設計図書等の文書を確認する「書面調査」と、現地で建材を目視で確認する「目視調査」からなり、これらによってアスベスト含有の有無が明らかにならない場合は、試料を採取して分析調査を行う必要があります。この一連の事前調査は、アスベストのレベルに関わらず、全ての解体・改修工事で実施しなければなりません。
レベル3アスベストにおける事前調査結果の報告・届出の要否
事前調査の結果は、電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて、労働基準監督署および管轄の地方自治体に報告することが義務付けられています。ただし、全ての工事で報告が必要なわけではなく、以下の要件に該当する場合に報告義務が生じます。
・ 建築物の解体工事:解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上
・ 建築物の改修工事:請負代金の合計額が100万円以上(税込)
・ 工作物の解体・改修工事:請負代金の合計額が100万円以上(税込)
したがって、例えば一般住宅の一部分の改修工事など、小規模な工事で上記の要件を満たさない場合は、事前調査の実施は義務ですが、その結果報告は不要となることがあります。また、これとは別に、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事の場合は、「建設リサイクル法」に基づく事前届出も必要となります。
一方で、レベル1やレベル2の建材を除去する際に必要な「特定粉じん排出等作業実施届出書」は、非飛散性とされるレベル3建材の除去作業では原則として不要です。ただし、自治体によっては独自の条例で報告を求めている場合があるため、事前に管轄の自治体に確認することが重要です。
「みなし判定」を選択した場合の事前調査と報告義務
重要な点として、「みなし判定」を選択したからといって、事前調査やその結果報告が免除されるわけではありません。みなし判定は、あくまで分析調査を省略する選択肢であり、書面調査と目視調査からなる事前調査自体は必須です。そして、その調査結果が前述の報告要件に該当する場合は、たとえ「みなし」でアスベスト有りと判断した場合でも、その旨を石綿事前調査結果報告システムで報告する義務があります。現場には調査結果の報告書を備え付け、作業者や関係者に周知するとともに、発注者への説明も必要です。
レベル3アスベストの適切な処理と安全対策
レベル3アスベスト建材は飛散性が低いとされていますが、不適切な方法で除去作業を行えば、アスベスト繊維が飛散し、作業者や周辺住民の健康を脅かす可能性があります。法令に基づいた適切な処理と安全対策が不可欠です。
レベル3アスベスト建材の除去作業における注意点
厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」では、レベル3建材の除去にあたり、以下の原則が示されています。
・ 原形のまま手作業で取り外す: 電動工具などによる切断や破砕は、粉じんを大量に発生させるため、極力避けるべきです。やむを得ず切断等を行う場合は、後述する湿潤化や集じん装置の使用が必須となります。
・ 湿潤化の徹底: 作業対象となる建材を、水や専用の湿潤剤で十分に湿らせることで、粉じんの飛散を大幅に抑制できます。作業中も乾燥しないよう、継続的に散水などを行うことが重要です。
・ 適切な保護具の着用: レベル3の作業であっても、発じんレベルに応じた防じんマスクの着用が義務付けられています。また、作業内容によっては保護衣や保護メガネの使用も推奨されます。
湿式作業の重要性と飛散防止対策
湿式作業(湿潤化)は、レベル3アスベストの除去作業における最も基本的かつ重要な飛散防止対策です。作業前に建材の表面だけでなく、切断面や裏面にも十分に水分を浸透させることが効果的です。特に、切断や穿孔を行う場合は、作業箇所に水をかけながら作業を行う「注水式」の工具を使用したり、集じん機付きの工具を使用して発生した粉じんを直ちに吸引するなどの対策が求められます。除去した建材は、飛散しないように湿潤な状態を保ち、耐水性の袋で二重に梱包するなどして、他の廃棄物と区別して保管・運搬します。
「みなし判定」時の最も厳しい措置とは?
前述の通り、みなし判定を選択した場合は、最も厳しい措置を講じる必要があります。これは、除去対象の建材に、最も危険性の高いアスベスト(クロシドライトなど)が、最も飛散しやすい状態で含まれていると仮定して対策を立てることを意味します。具体的には、以下のようなレベル1に準じた措置が求められる可能性があります。
・ 作業場所の隔離: 作業区域をプラスチックシートなどで完全に隔離し、外部に粉じんが漏洩しないようにします。
・ 負圧除じん装置の使用: 隔離した作業場所の内部を外部より低い気圧(負圧)に保ち、粉じんが外部に流出するのを防ぎます。
・ 高レベルの保護具: 電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)や、使い捨ての防護服、保護メガネ、手袋など、より高度な保護具の着用が求められます。
これらの措置は、通常のレベル3作業に比べて大幅なコスト増と工期の延長につながるため、みなし判定の判断は慎重に行う必要があります。
アスベスト関連法規と今後の動向
アスベスト問題への対応は、社会的な要請の高まりとともに、法規制が年々強化されています。最新の動向を把握し、法令を遵守することが事業者には求められます。
アスベスト関連法規の概要とレベル3への適用
アスベスト対策は、主に以下の法律によって規制されています。
・ 大気汚染防止法: 建築物の解体等工事におけるアスベストの飛散防止を目的とし、事前調査、作業基準の遵守、都道府県等への届出などを定めています。レベル3建材も、事前調査や作業基準の遵守義務の対象となります。
・ 石綿障害予防規則(労働安全衛生法): 労働者のアスベストばく露防止を目的とし、事前調査、作業計画の策定、作業主任者の選任、保護具の使用、健康診断などを定めています。レベル3の作業も、この規則の対象です。
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律: アスベスト含有廃棄物を「特別管理産業廃棄物」または「石綿含有産業廃棄物」として定義し、その収集、運搬、処分に関する基準を定めています。レベル3建材から発生した廃棄物も、この法律に従って適正に処理しなければなりません。
法改正のポイントと最新情報
アスベストに関する法規制は、近年、段階的に強化されています。2021年4月からは、アスベスト含有成形板等(レベル3)の除去作業において、切断・破砕等を行う場合に作業基準の遵守が義務化されました。さらに、2022年4月からは事前調査結果の電子報告制度が開始され、2023年10月からは事前調査を行うための調査者の資格要件が厳格化されました。今後も、既存建築物に多く残存するアスベストの除去が本格化するにつれて、さらなる規制強化や新たな技術的指針が示される可能性があります。事業者は、常に最新の情報を収集し、法令遵守体制を維持することが重要です。
専門業者に依頼する重要性
アスベストの調査から除去、廃棄物処理に至るまでの一連の作業は、高度な専門知識と技術、そして厳格な法規制への準拠が求められます。不適切な作業は、作業者や周辺住民の健康に深刻な被害を及ぼすだけでなく、事業者自身も厳しい罰則(懲役や罰金)の対象となります。特に、みなし判定の判断や、適切な作業レベルの見極め、各種届出の要否など、専門家でなければ判断が難しい場面も少なくありません。リスクを確実に回避し、安全かつ適法に工事を進めるためには、信頼できるアスベスト専門の調査会社や工事業者に相談・依頼することが最も確実な方法と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、アスベストレベル3に焦点を当て、その特徴から「みなし判定」の仕組み、事前調査・届出の義務、そして適切な除去作業の方法に至るまでを網羅的に解説しました。レベル3は飛散性が低いとされていますが、作業方法を誤れば重大な健康被害につながるリスクをはらんでいます。特に「みなし判定」は、分析調査のコストを削減できる可能性がある一方で、かえって対策費用が増大するリスクも伴うため、慎重な判断が求められます。強化され続ける法規制を正確に理解し、遵守することは、事業者の社会的責務です。アスベストに関する疑問や不安がある場合は、決して自己判断せず、必ず専門の資格を持つ調査会社や工事業者に相談し、安全を最優先した対策を講じるようにしてください。
参考文献
・ 国土交通省「1−1 アスベストの飛散性・非飛散性とレベル1〜3の整理」https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/asbestos/2pdf/s1-1.pdf
・ 厚生労働省「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000199665.pdf
・ 環境省「石綿事前調査結果の報告について」https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
・ 厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」https://www.mhlw.go.jp/content/000919436.pdf