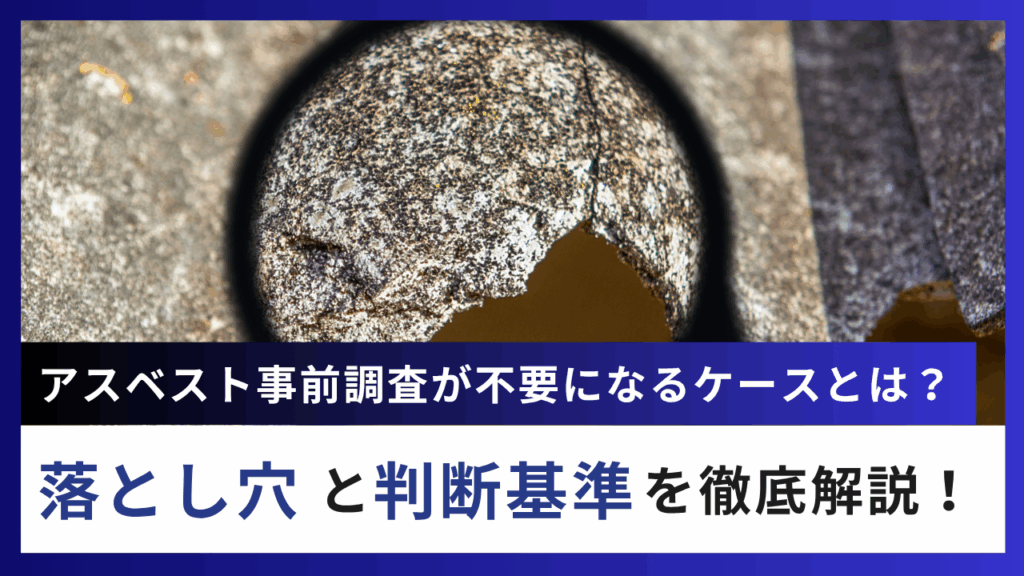建築物の解体や改修工事を行う際、アスベスト(石綿)の事前調査は原則として義務付けられています。しかし、全ての工事で事前調査が必要となるわけではありません。アスベストを含まないことが明らかな建材のみを扱う場合や、アスベスト含有建材を損傷させない軽微な作業など、特定の条件下では事前調査が不要となるケースが存在します。本記事では、アスベスト事前調査が不要となる具体的な条件を、厚生労働省の「石綿障害予防規則」に基づき詳細に解説し、見落としがちな注意点や判断基準を明確にすることで、安全かつ適正な工事計画の立案を支援します。
アスベスト事前調査の基本と義務付けの背景
アスベスト事前調査の「不要」ケースを理解するためには、まずアスベスト事前調査がどのようなもので、なぜ義務付けられているのかを正確に把握することが重要です。アスベストは、その繊維が飛散し吸入されることで、肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こす危険性があるため、厳格な規制が設けられています。
アスベスト事前調査とは
アスベスト事前調査とは、建築物の解体や改修等の工事を行う前に、対象となる建築物や工作物、船舶にアスベスト含有建材が使用されているかどうかを、書面調査、目視調査、そして必要に応じて分析調査によって確認するものです 。この調査は、工事中にアスベストが飛散し、作業者や周辺住民の健康を害するリスクを未然に防ぐことを目的としています。
調査の結果は、労働基準監督署や管轄の自治体へ報告することが義務付けられています。この報告制度は、2020年に義務化された「石綿障害予防規則(石綿則)」の段階的な法改正によって施行されたものです 。
アスベスト事前調査が義務付けられる工事の範囲
アスベスト事前調査は、原則として全ての解体・改修工事において義務付けられています。特に、アスベストの使用が全面禁止された平成18年(2006年)9月1日以前に着工された古い建物においては、ほぼ例外なく事前調査が必須となります。調査と報告が必要となる工事の具体的な範囲は以下の通りです :
・ 建築物の解体工事:解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上の場合
・ 建築物の改修工事:請負代金の合計額が100万円以上(税込)の場合
・ 工作物の解体・改修工事:請負代金の合計額が100万円以上(税込)の場合
・ 鋼製の船舶の解体または改修工事:総トン数20トン以上の場合
これらの工事以外でも、エアコン設置のための穴あけや配管工事など、軽微に見える作業であってもアスベスト含有建材を損傷する可能性がある場合は、事前調査が必要となることがあります。アスベストの飛散を未然に防ぐため、現在では軽微なものから大規模なものまで、あらゆる工事において事前調査が義務付けられていると理解しておくべきです 。
調査は資格保有者のみが実施可能
アスベストの事前調査は、専門的な知識を持った資格保有者、またはそれと同等の知識を有すると認められた者のみが行うことができます。具体的には、「一般建築物石綿含有建材調査者」「特定建築物石綿含有建材調査者」「工作物石綿事前調査者(新設予定)」などの資格が必要です。加えて、厚生労働省が実施するアスベスト調査関連の講習を修了していることも条件となります。元請業者は、これらの資格を持つ専門家へ調査を依頼するか、自社の従業員が資格を取得して調査を進める必要があります。
アスベスト事前調査が「不要」となる具体的なケース
アスベスト事前調査は原則義務ですが、特定の条件下では調査が不要、または一部の調査が省略できるケースがあります。これらのケースは、「アスベストを含む建材の使用が無いことがほぼ確実だとされる工事」に限定されます。
1. アスベストを含まないことが明らかな建材に係る工事
対象となる建材自体にアスベストが含有されていないことが明確な場合、事前調査は不要とされます。具体的には、ガラス、木材、石など、素材自体にアスベストが混合されない建材のみを対象とした工事がこれに該当します。
ただし、この場合でも注意が必要です。例えば、ガラスや木材を取り外す際に、周囲にアスベスト含有の可能性がある材料を損傷させてしまう恐れがある場合は、事前調査が必要となります。あくまで「アスベストを含まないことが明らかな建材”のみ”を対象とした工事」であることが条件です。
2. アスベスト含有建材を損傷・飛散させずに除去できる軽作業
アスベスト含有建材が存在する場合でも、その建材を損傷させたり、アスベストを飛散させたりするリスクが極めて低い軽作業においては、事前調査が不要となることがあります。具体的には、手作業でネジやボルトを外す、釘を打つ・抜くといった作業が該当します。
しかし、電動工具を用いた穴あけ作業など、アスベスト含有建材を損傷させる可能性のある作業は、軽作業とはみなされず、事前調査が必要となります。作業内容がアスベスト飛散のリスクを伴わないか、慎重な判断が求められます。
3. アスベスト含有建材の除去等をせず材料追加のみの作業
アスベスト含有建材そのものを除去せず、新たな材料を追加する作業についても事前調査が不要となる場合があります。例えば、アスベスト含有の可能性がある建材の上からそのまま塗料を塗る作業などがこれに該当します。
しかし、塗装を行う際に既存の塗料を剥がす作業が含まれる場合、アスベストが飛散するリスクが生じるため、事前調査が必要になります。また、壁紙の張り替えなども、下地の状況によっては事前調査の対象となることがあるため注意が必要です。
4. 過去に事前調査が行われている、または事前調査相当の検査が済んでいる場合
基本的にアスベストの事前調査は「工事ごとに必要」とされています。しかし、過去にアスベスト事前調査が行われており、その調査結果が「石綿障害予防規則第3条第2項第1号及び第2号に規定する方法に相当する」と認められる場合は、新たな事前調査が不要となるケースがあります [1]。
具体的には、前回の調査で建築物における工事対象の建材が全て調査済みであり、その調査結果の記録を確認することで、改めて事前調査を行う必要はないとされています。ここでいう「第3条第2項第1号及び第2号に規定する方法」とは、設計図書等の文書確認と目視による確認を指します [1]。
つまり、過去の調査で全ての建材について書面および目視による調査が適切に行われ、その記録が現在も変更されていないことが確認できる場合に限り、保管記録の確認のみで足りるとされます。ただし、これは非常に限定的なケースであり、多くの場合、過去の調査記録との照合のために目視調査が必要となるため、厳密には事前調査に準ずる作業が発生すると考えられます。アスベスト事前調査の記録は3年間の保管義務があるため、その期間内で確認することが望ましいでしょう。
5. 平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建築物
アスベストの使用が全面禁止された平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建築物については、原則としてアスベスト含有建材が使用されていないと考えられます。このため、設計図書等で着工日を確認し、この期日以降であることが確認できれば、書面調査のみで問題ないとされています [1]。
この場合、資格保有者以外の者でも着工日の確認を行うことができます。ただし、解体工事の規模によっては、着工前の事前調査結果の行政報告や、発注者への説明、事前調査結果の現場への掲示が必要となる場合があります。これは、アスベストが確実に存在しない場合でも、一定規模以上の解体工事では報告義務が生じるためです。
事前調査不要ケースの判断における注意点とリスク
アスベスト事前調査が不要となるケースは限定的であり、誤った判断は重大な健康被害や法的罰則につながる可能性があります。ここでは、判断における注意点と潜在的なリスクについて解説します。
専門家による最終判断の重要性
上記で挙げた「事前調査が不要となるケース」は、あくまで原則的なものです。実際には、建物の構造、過去の改修履歴、使用されている建材の種類など、様々な要因が複雑に絡み合っています。例えば、「アスベストを含まないことが明らかな建材」と判断しても、その裏側にアスベスト含有建材が隠れている可能性も否定できません。
そのため、事前調査の要否を最終的に判断する際には、必ずアスベストに関する専門知識と資格を持つ専門家(石綿含有建材調査者など)に相談し、現地状況を詳細に確認してもらうことが不可欠です。専門家は、設計図書と現場の状況を照合し、リスクを総合的に評価することで、最も安全かつ適切な判断を下すことができます。自己判断による誤りは、取り返しのつかない結果を招く可能性があるため、絶対に避けるべきです。
軽微な作業の定義と電動工具の使用
「アスベスト含有建材を損傷・飛散させずに除去できる軽作業」は事前調査が不要となるケースの一つですが、この「軽作業」の定義は非常に厳格です。手作業による釘打ちやネジ外しなどが該当しますが、電動工具を用いた作業は、たとえ小さな穴を開けるだけでもアスベスト繊維を飛散させるリスクがあるため、原則として事前調査が必要です。
作業の規模や内容が「軽微」であると自己判断せず、少しでも疑問がある場合は専門家に確認することが重要です。特に、電動工具を使用する可能性がある場合は、必ず事前調査を行うべきだと認識しておきましょう。
過去の調査記録の信頼性
過去の事前調査結果がある場合でも、その記録の信頼性を慎重に評価する必要があります。記録が古すぎる場合や、調査範囲が不明確な場合、あるいはその後の改修工事で新たなアスベスト含有建材が追加された可能性も考慮しなければなりません。
「石綿障害予防規則」では、過去の調査が現在の規則に相当する方法で行われた場合に限り、その記録の確認で足りるとされています [1]。しかし、この「相当する方法」であるかどうかの判断自体が専門知識を要するため、安易に過去の記録のみで判断することは危険です。記録の有効性についても専門家の意見を求めるべきでしょう。
法改正と罰則のリスク
アスベストに関する法規制は、健康被害防止の観点から年々強化されています。事前調査義務を怠った場合や、虚偽の報告を行った場合には、罰則が科せられる可能性があります。例えば、石綿障害予防規則に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰が適用されることがあります。
また、事前調査を適切に行わなかった結果、アスベスト飛散による健康被害が発生した場合には、民事上の損害賠償責任を問われる可能性もあります。これらの法的リスクを回避するためにも、常に最新の法規制を把握し、適正な手続きを踏むことが求められます。
アスベスト事前調査の適切な進め方
アスベスト事前調査が不要となるケースは限定的であるため、多くの工事では適切な事前調査の実施が不可欠です。ここでは、一般的な事前調査の流れと、専門業者に依頼するメリットについて解説します。
一般的な事前調査の流れ
アスベスト事前調査は、以下の3つの段階で進められます:
1.書面調査:建築物の設計図書や竣工図、過去の改修記録などを確認し、建設時の着工日や使用建材、アスベストの使用履歴などを総合的に調査します。平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建物であれば、書面調査のみでアスベスト不使用と判断できる場合があります。
2.目視調査:書面調査で情報が不十分な場合や、書面調査の結果と現場状況に相違がある場合に、現地で建材を目視で確認します。建材の種類や劣化状況、アスベスト含有の可能性を評価します。
3.分析調査:書面調査や目視調査でアスベスト含有の有無が判断できない場合、または含有の可能性が高いと判断された場合に、建材の一部を採取して専門機関で分析します。これにより、アスベストの種類や含有率を正確に特定します。分析を行わない場合は、「みなし判定(アスベスト有とみなして着工)」を選択することも可能です。
これらの調査を経て、最終的な事前調査報告書が作成され、関係機関への報告が完了した後、工事に着工となります。
専門業者に依頼するメリット
アスベスト事前調査は、専門的な知識と経験、そして資格が求められる複雑な作業です。そのため、自社で対応が難しい場合は、アスベスト調査・分析の専門業者に依頼することが最も確実で安全な方法です。
専門業者に依頼するメリットは以下の通りです:
・ 法的要件の遵守:最新の法規制やガイドラインに基づき、適正な調査を実施します。これにより、法的リスクを回避できます。
・ 正確な判断:豊富な経験と専門知識を持つ資格保有者が、建材の識別やリスク評価を正確に行います。これにより、アスベストの見落としや誤判断のリスクを最小限に抑えられます。
・ 安全性の確保:アスベスト飛散防止のための適切な措置を講じながら調査を進め、作業者や周辺環境の安全を確保します。
・ 効率的な工事計画:調査結果に基づき、アスベストの除去や封じ込めが必要な場合の最適な対策を提案し、スムーズな工事計画をサポートします。
・ 報告業務の代行:労働基準監督署や自治体への報告業務を代行してくれるため、事業者側の負担を軽減できます。
アスベスト事前調査の要否判断に迷う場合や、専門的な対応が必要な場合は、迷わず専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
まとめ
アスベスト事前調査は、建築物の解体・改修工事におけるアスベスト飛散による健康被害を防止するために不可欠な義務です。原則として全ての工事で必要とされますが、本記事で解説した以下の特定のケースでは、事前調査が不要となる場合があります。
・ アスベストを含まないことが明らかな建材のみを扱う工事
・ アスベスト含有建材を損傷・飛散させずに除去できる軽作業
・ アスベスト含有建材の除去等をせず材料追加のみを行う作業
・ 過去に適切な事前調査が行われ、その記録が有効な場合
・ 平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建築物
しかし、これらの「不要」ケースの判断は非常に専門的であり、自己判断は大きなリスクを伴います。特に、軽微な作業の定義や過去の調査記録の信頼性、そして最新の法規制の遵守には細心の注意が必要です。誤った判断は、健康被害だけでなく、法的罰則や民事上の責任につながる可能性もあります。
安全かつ適正な工事を進めるためには、アスベスト事前調査の要否判断に迷うことなく、必ず専門知識と資格を持つ「石綿含有建材調査者」などの専門家に相談し、適切なアドバイスと調査を依頼することが最も重要です。専門家の知見を活用することで、アスベスト関連のリスクを最小限に抑え、安心して工事を進めることができるでしょう。
参考文献
[1] e-Gov法令検索「石綿障害予防規則」(最終閲覧日:2025年10月21日)https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021