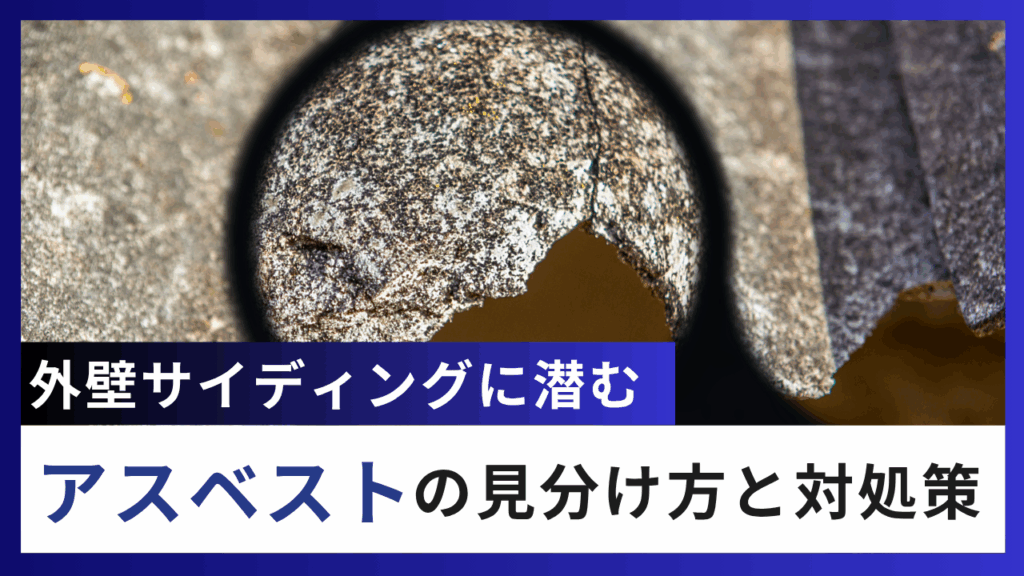アスベストとサイディングの基本をおさえる
建物の外壁によく使用される「サイディング材」には、過去にアスベスト(石綿)が含まれていた製品が存在しています。特に1970年代から2000年代初頭までの間に建築された建物では、使用リスクが残っており、法人にとって無視できない検討項目です。この記事では、サイディング材の基本的な知識やアスベストとの関係性を整理し、注意すべきポイントを解説します。
サイディング材の種類と特徴:どれに注意すべき?
サイディングとは、建物の外装を覆うためのパネル状の建材で、施工のしやすさやコスト面から広く普及しています。主に次の4種類が存在します。
・ 窯業系サイディング(セメント系):耐火性が高く、90年代以降の住宅に多く使用。
・ 金属系サイディング(アルミやガルバリウム鋼板):軽量で耐久性が高い。
・ 樹脂系サイディング:アメリカで多用、日本ではあまり一般的でない。
・ 木質系サイディング:デザイン性が高いが、耐火性の確保に課題あり。
この中でも特に注意すべきは「窯業系サイディング」です。セメントの補強材として1970~2004年頃までアスベストが混入された製品が多く出回っており、法人としては施工年代と種類を正確に把握しておく必要があります。
アスベストが建材に使用された理由とは?
アスベストは、耐熱性・絶縁性・耐摩耗性に優れる鉱物繊維であり、「万能素材」としてかつて建築分野で広く使用されていました。サイディングに使用された主な理由は以下の通りです。
・ セメントに混ぜることで強度を向上させ、耐ひび割れ性が高まるため
・ 外壁材としての防火性を高め、耐火建築に適していたため
・ 加工のしやすさとコストの低さにより、量産に向いていたため
当時は法規制もなく、アスベストを添加したサイディングが大手メーカーからも数多く販売されていました。しかし、健康被害が問題視され始めたことで段階的に使用禁止となり、現在ではその使用が完全に禁止されています。
アスベスト入りサイディングが使われた時代と背景を読み解く
アスベストが外壁材として使われていた背景を知ることは、建物のリスク管理を行ううえで欠かせません。ここでは、いつ頃からアスベストが使われ始め、どのように規制が進んだのか、そして現在でも残るリスクについて詳しく解説します。
1970年代から広がった使用と普及の経緯
日本において、アスベストがサイディングに使われ始めたのは1970年代前半。この頃、窯業系サイディングにアスベストを混入することで、耐熱性や施工性が向上し、特にセメント系建材との相性が良かったことから急速に普及していきました。
当時は高度経済成長の真っ只中で、住宅やオフィス、工場などの新築が相次ぎ、建材にも「安価・大量・短納期」が求められていました。アスベストは、これらのニーズに最適な素材として評価され、建材メーカーの多くが採用していたのです。法人が所有している建物のうち、1970年代から1990年代後半までに建てられたものは、アスベスト含有の可能性が高いと認識しておくべきです。
2004年〜2006年の法改正が分岐点に
アスベストに対する法的な規制が強化されたのは2000年代に入ってからです。まず2004年には、「含有率1%超」のアスベスト建材の製造・使用が禁止され、さらに2006年にはその基準が「0.1%超」にまで引き下げられました。これにより、事実上すべてのアスベスト使用が禁止されることとなります。
この2004~2006年の期間は、アスベスト対策における「規制の転換期」と言えます。多くの建材メーカーがこの時期にアスベストフリー製品へと切り替えを進めました。ただし注意すべきは、すべての現場でこの切替がスムーズに行われたわけではないという点です。とくに中小メーカーや地域によっては、既存の在庫品をそのまま使用していたケースも存在しています。
在庫建材によるアスベスト残存リスクに注意
たとえ2006年以降に建てられた建物であっても、アスベストが含まれている可能性はゼロではありません。というのも、建材が実際に使われるまでには「製造」「流通」「保管」「施工」といった複数の段階があり、現場に届いたタイミングが必ずしも規制以降とは限らないからです。
とくに地方では、コストの関係や在庫処分を目的に、規制前の建材がそのまま使われたケースも報告されています。つまり「建築年」だけでアスベストの有無を判断するのは不十分なのです。対応する際は、以下のような情報を複合的に確認する必要があります。
・ 建材の型番や製品ラベルの記録
・ 当時の施工業者や流通業者の履歴
・ 納品書や建築資料からの建材情報の特定
・ 専門業者によるサンプル採取と成分分析の実施
建築年から読み解くアスベストの可能性と見極め方
アスベストが含まれているかどうかは、建材を見ただけでは判断が難しいため、建築年代や使用された建材情報をもとに推測していく必要があります。とくに、改修や解体を予定している建物にアスベストのリスクがあるかを事前に把握することが、安全対策・コスト見積もり・法令対応のいずれの面でも重要なポイントになります。ここでは、実務で役立つ3つの判断方法をご紹介します。
建築時期や改修履歴をもとに初期判断を行う
最初の手がかりとなるのが「建築年」や「外壁の改修年」です。以下の基準を参考にすれば、おおよそのリスクを見積もることができます。
2006年以降に建築・改修された建物
→ 原則としてアスベストを含む建材は使われていない可能性が高い
2004年以前に建築・リフォームされた建物
→ アスベスト使用の可能性が非常に高い
2004〜2006年の施工物件
→ 移行期のため、在庫品などにより含有のリスクが残る
これらはあくまで「目安」であり、例外も存在します。まず所有する建物の記録や工事履歴を確認し、施工年の特定を優先しましょう。
建材の型番やラベル情報で製品特定を試みる
次に重要なのが、実際に使用された建材の「型番」や「製品名」です。建物の軒下や裏側にメーカーのラベルが残っている場合や、過去の工事記録に品番が記載されていることがあります。一部の大手メーカーでは、過去の建材についてアスベストの含有有無を公表しており、型番や製品コードで判別できることもあります。「AF(アスベストフリー)」などの記載がある場合は、非含有の可能性が高いと判断できます。
調査時にチェックすべきポイント:
・ 製品ラベルやシールの有無
・ 工事記録・納品書などに記された型番情報
・ 製造メーカーへの直接照会も視野に入れる
石綿含有建材データベースの有効活用法
国土交通省と厚生労働省が共同で整備している「石綿含有建材データベース」は、公的にアスベストの有無を確認できる便利なツールです。製品名や型番を入力すれば、アスベストが含まれているか、または不明なのかを判定することができます。このデータベースには、サイディング材だけでなく、けい酸カルシウム板や化粧石膏ボードなどさまざまな建材が掲載されており、無料で誰でも利用可能です。
データベースを使う手順
STEP1:建材の製品名やメーカーを特定
STEP2:石綿含有建材データベースにアクセス
STEP3:情報を入力して検索
STEP4:「含有」「非含有」「不明」いずれかの結果を確認
調査会社に依頼する前の事前確認としても有用で、スムーズな対応計画に役立ちます。
知っておきたいアスベストに関する主要な法令と義務
企業がアスベストリスクに適切に対応するためには、以下の法制度に則った対策が不可欠です。
労働安全衛生法
→ 工事前の事前調査義務/作業主任者の配置/作業環境の測定が必要
大気汚染防止法
→ アスベストの飛散防止措置と作業届出が義務付けられている
建築基準法
→ 新築・増改築におけるアスベスト使用の原則禁止
廃棄物処理法
→ アスベスト含有建材は「特別管理産業廃棄物」として適切な処理が必要
なかでも注意すべきは「事前調査の未実施」に対する罰則です。調査を怠って着工した場合、50万円以下の罰金が科されることがあり、また、たとえ下請け業者に委託していたとしても、元請け企業には最終的な責任が及びます。損害賠償リスクも含め、法令遵守は企業として絶対に外せない対応です。
管理体制で備えるアスベスト対策の基本フレーム
アスベストリスクへの対応においては、単発の措置では限界があり、継続的かつ組織的なリスクマネジメント体制の構築が必要です。まず、管理物件ごとに施工年や修繕履歴を把握し、一覧化することでリスクの所在を明確にすることが重要です。さらに、使用されている建材のメーカーや型番などの情報を正確に記録・保管できる体制を整えることで、将来的な調査や対策が円滑に進められるようになります。
また、アスベストの有無を確認するための調査を、改修や解体などの工事発注プロセスの中にあらかじめ組み込むといった、運用ルールの整備も不可欠です。外注業者を含めた関係者への労働安全に関する教育を、定期的に実施することで、現場レベルでの安全意識を高めることができます。
加えて、アスベスト対策にかかる費用については、事前に予算として確保し、責任を担う部署を明確にしておくことも、円滑な対応につながります。実際に改修や解体工事を行う際には、法務部門、総務部門、建物管理部門など、複数の部門が密に連携し、迅速に判断・対応できる体制を築いておくことが理想的です。さらに、内部通報制度や安全監査制度を整えることで、リスクの早期発見と未然防止を図ることができ、組織全体としてのアスベストリスク管理能力が高まるでしょう。
建物所有者が講じるべきアスベスト調査と対策フローの実務対応
アスベストに関するリスクは、見過ごすと重大な法的・社会的問題に発展する恐れがあります。建物の所有者として責任を果たすには、制度に基づいた調査と対応フローを整備することが不可欠です。ここでは、アスベストが含まれている可能性がある建物に対し、実施すべき基本的なステップをご紹介します。
調査の依頼時期と実施ステップの流れ
アスベストの調査は、一定の条件下で法的に義務付けられているほか、リスク管理の観点からも強く推奨される場面があります。たとえば、改修工事や解体工事を計画しているケースや、1970年から2006年の間に建設された建物を所有している場合には、アスベストの使用有無を確認する必要があります。また、建材の仕様や使用履歴が不明で、設計図や記録が不十分な建物についても、念のための調査を行うことが望まれます。
調査の進め方としては、まず建物の築年数や施工内容を確認するため、台帳や設計図などの資料を収集することから始まります。その後、施工を担当した建設会社やアスベスト調査に対応可能な業者に相談し、現地での調査が可能かどうかを判断します。調査の必要があると判断された場合には、サイディング材など建材の一部を採取し、成分の分析を専門機関に依頼します。分析結果が出た後は、それに基づいてアスベストの有無や含有量を確認し、必要に応じて「除去」「封じ込め」「囲い込み」といった対応方針を検討していきます。
このような調査を依頼する際には、建築士事務所、解体業者、環境調査会社など、石綿に関する知見を有する専門事業者が対応します。中でも、建築物石綿含有建材調査者やアスベスト診断士など、資格を持ったスタッフが在籍しているかどうかは、業者選定の際に重視すべきポイントです。信頼できる専門業者と連携し、正確かつ安全な調査・対応を進めることが、リスク回避の第一歩となります。
調査結果に応じた対応の選択肢と判断ポイント
調査の結果、アスベストの含有が確認された場合には、以下の3つの対応方法から適切な手段を選ぶ必要があります。
除去:建材ごと撤去する方法。飛散防止の措置や届出が必須
封じ込め:アスベストが飛散しないよう、専用資材で覆って処理する
囲い込み:建材を壁や天井の二重構造で覆い、接触や飛散を防ぐ措置
除去工事を選択する場合、工事の14日前までに都道府県や政令指定都市への「作業届」の提出が必要です。また、アスベストを含む建材は「特別管理産業廃棄物」として処理しなければならず、収集運搬・中間処理・最終処分の各段階で法的管理が求められます。
そのため、調査段階からこれらの対応費用やスケジュールを見込んでおくことが、工期遅延や予算超過を防ぐうえでも重要です。