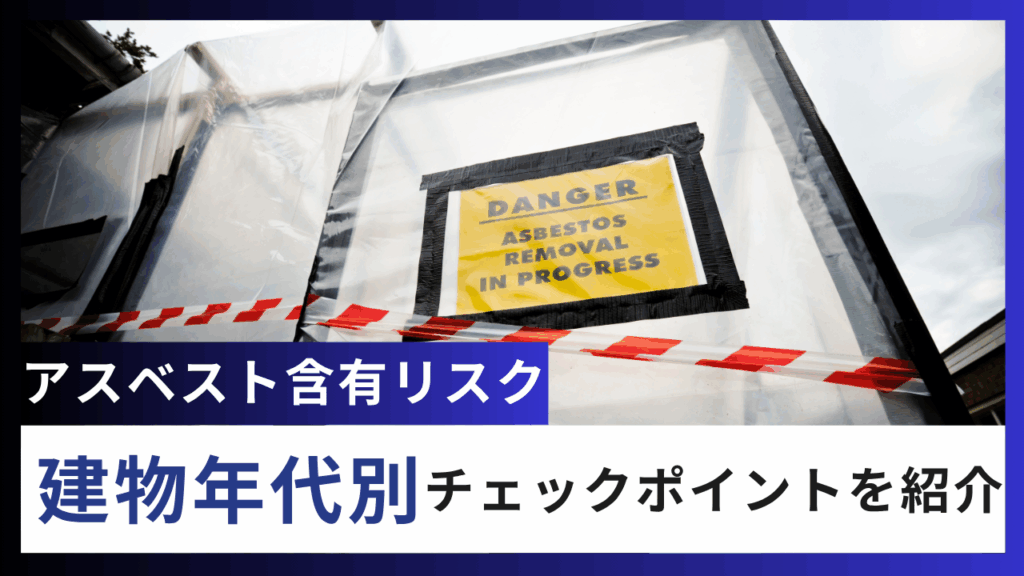アスベストと建物年代の関係性を押さえる
建物にアスベストが使われているかどうかは、建物の年代、つまり築年数が大きな目安となります。これは、アスベストが日本国内で使用されはじめた時期と、法規制が施行された時期に強く関連しているためです。
法人施設やビル、工場、公共施設などの管理を担当されている方にとって、所有・管理する建物がアスベスト含有建材を使用しているかどうかは、労働安全衛生法や建築基準法に基づく管理義務に関わります。例えば、1970年代以前に建てられた建物は、アスベスト使用の可能性が非常に高いとされています。一方で2006年以降は全面禁止となっているため、原則として新築物件には含まれていません。ただし、実際の使用状況は個別に確認が必要です。
この記事では、なぜ築年数がアスベスト調査や管理判断の目安となるのか、その基本的な考え方を解説します。
なぜ築年数がアスベスト使用リスクの目安になるのか
アスベストは、かつて建材や断熱材、吹付け材として広く使用されてきた素材であり、高い耐熱性・耐久性・防音性を兼ね備えていることから、さまざまな建物で活用されてきました。しかし、その健康被害が深刻な社会問題となったことを背景に、日本国内でも段階的に規制が進められました。
こうした経緯から、どの年代までアスベスト含有建材が使われていたのかを把握することは、その建物にアスベスト含有リスクがあるかどうかを判断する上で、非常に重要な指標となります。業種や施設規模にかかわらず、管理者がアスベストリスクを正しく認識し、必要な調査や対策を講じることが求められています。
ただし、築年数だけで必ずしもアスベスト使用の有無を完全に判断できるわけではありません。設計・施工時期のズレや改修履歴など、年代以外の要素も考慮する必要があります。
アスベストに関する法律改正による使用規制の流れ
日本国内におけるアスベスト建材の使用状況は、法規制の変遷と密接に関係しています。以下はその主な流れです。
・1975年以前:ほぼ無規制。吹付け材や断熱材などに広く使用。
・1975年〜1985年:段階的な規制開始。吹付けアスベストなど特定用途が禁止。
・1986年〜2006年:使用制限対象が拡大し、最終的に2006年には全面禁止。
この流れを踏まえると、法人施設などでアスベスト調査を行う際は、「建物の確認申請日」や「竣工日」を必ずチェックする必要があります。特に1975〜2006年の間は規制が移行期であるため、年代だけでなく用途や建材種類まで調べる必要があります。
また、法改正のタイミングと建築現場での材料使用にはタイムラグがあるため、完全に安心できるラインは2007年以降と言われています。
建物年代別アスベスト含有リスク一覧
アスベスト含有リスクは、建物が建てられた年代ごとに大きく変わります。法人施設やビルの管理を行う際には、以下の年代区分を参考に、自社施設がどのリスクレベルに該当するか確認することをおすすめします。
ここでは「1975年以前」「1976年〜2006年」「2007年以降」の3つの区分に分けて、建物年代別の特徴と注意点を詳しく解説します。
1975年以前:アスベスト使用リスクと注意点
1975年以前に建築された建物は、アスベスト使用リスクが最も高い年代に該当します。この時期はアスベスト規制がほぼ存在せず、あらゆる建材に使用されていた時代です。
1975年以前の建物を所有・管理している法人は、ほぼ確実に専門業者によるアスベスト調査が必要となります。また、この時代の建物は老朽化が進んでいるケースも多く、解体や大規模改修の際には必ず法令に基づく事前調査義務があります。
【注意ポイント】
・築年数が古いだけでなく、改修歴がない場合は特にリスク大
・目視だけでは判断できないため、必ず専門調査を実施すること
・事前調査・報告義務違反には罰則が科せられる可能性あり
1976年〜2006年:規制移行期の建物に潜むリスク
1976年以降、厚生労働省や建築関連法規によりアスベスト使用規制が段階的に進められてきました。しかし、全面禁止となった2006年までは、用途によっては一部アスベスト建材が合法的に流通・使用されていた期間でもあります。
そのため、この期間に建てられた建物は「一部にアスベストが含まれている可能性があるグレーゾーン」と考えるべきです。
【注意ポイント】
・使用禁止対象外だった建材にアスベスト含有があるケースあり
・解体や改修の際は法令確認が必須
2007年以降:アスベストリスクは完全にゼロか?
2006年9月の労働安全衛生法などの改正により、アスベスト(石綿)を含むすべての建材は、原則として製造・使用が禁止されました。これにより、2007年以降に竣工した建物については、アスベストが含まれている可能性は極めて低いと考えられています。
しかしながら、いくつか注意すべき点もあります。たとえば、海外製の建材を輸入したケースでは、アスベストが含まれていた事例があります。また、規制前に製造された建材の在庫品や、不正に流通した製品が使われた可能性も否定できません。さらに、施工業者が誤ってアスベスト含有建材を使用したり、アスベストのリスクについて十分な知識がなかったりする場合もあります。
特に法人施設では、コスト削減のために安価な海外製建材を採用することがあり、その際には製品のアスベスト含有証明書や納品書を確認しておくとより安心です。
【注意ポイント】
・2007年以降でも完全なゼロリスクとは言い切れない
・疑わしい場合は建材サンプル分析などの専門調査を実施
アスベスト含有リスクは建物年代だけでは判断できない3つの理由
建物が建てられた年代を確認することで、アスベスト含有リスクのおおよその目安をつけることは可能です。しかし、実際の現場では「年代だけでは判断しきれない」ケースも多々あります。
ここでは法人施設の管理担当者が特に注意すべき、建物年代だけでは判断できない3つの理由を解説します。これらを理解したうえで、正確な調査・管理対応を行うことが大切です。
理由1:施工時期と設計時期のズレ
建築物は「設計から着工、そして竣工に至るまで」、通常は数ヶ月から数年にわたる期間を要します。特に大規模な施設やビル、公共建築物などでは、この期間がさらに長引く傾向にあります。たとえば、建築確認申請が2006年以前に行われ、同時に建材の発注も完了していた場合、その建物が実際に完成したのが2007年以降であっても、2006年以前のアスベスト含有建材が使用されている可能性があります。
法人施設では、実際に着工から竣工まで2年以上かかったビルや、設計変更によって着工が遅れた案件、さらには公共事業で工期が延長されたケースなどが見受けられます。こうした背景を踏まえると、建物の安全性を確認する際には、単に竣工日だけを見るのではなく、建築確認日と併せて確認することが重要です。また、建材の発注履歴や納品書の有無も確認できれば、より正確な判断につながります。
理由2:リフォームや改修による混在リスク
建物は新築のまま使い続けられることはほとんどなく、多くの場合、途中で改修やリフォームが行われます。現在ではアスベスト含有建材の使用は禁止されていますが、改修工事が2006年以前に実施されていた場合には注意が必要です。
たとえば1990年代の内装リフォームや、屋根・外壁の補修、テナント入れ替え時の内装工事などでは、アスベスト建材が使われていた可能性があります。建物自体が新しく見えても、一部に古い建材が混在しているケースは法人施設で多く見受けられます。
安全確認のためには、建物台帳や工事履歴の確認が重要です。履歴が不明な場合は、専門業者による全体調査を依頼することをおすすめします。
理由3:違法建材や古い在庫品使用の可能性
アスベストを含む建材の製造や使用が法律で禁止された後も、一部の現場では「在庫品」や「違法流通品」が使われた事例が報告されています。背景には、コスト削減を目的とした悪質業者による不正使用や、海外からの安価な建材の輸入、小規模な工事現場での規制への認識不足などが挙げられます。
法人施設においては、大手ゼネコンが関与する大規模建築であれば比較的リスクは低いものの、中小規模のリフォームや部分的な工事では十分な注意が必要です。2007年以降の建物であっても、必ずしも安全とは限らないことを前提に、疑わしい箇所がある場合にはサンプル採取や分析検査を実施することが安心につながります。
まとめ:押さえるべきアスベスト調査ポイント
法人施設やビルの管理に携わる皆さまにとって、アスベスト問題は決して過去の話ではなく、現在進行形のリスク管理課題です。特に建物の年代によってアスベスト含有リスクが大きく異なるため、まずは自社施設の築年数をしっかりと確認することが第一歩となります。
1975年以前に建てられた建物は、吹付け材や断熱材などさまざまな用途でアスベストが使われていた時代です。1976年から2006年の間は段階的な規制期間となっており、一部用途での使用が継続されていたため、グレーゾーンとして慎重な対応が求められます。そして2007年以降の建物でも、完全にリスクゼロとは言い切れないことから、万全を期す姿勢が重要です。ただし、建物年代だけでは判断できない場合も多々あります。設計時期と竣工時期のズレや、過去に行ったリフォームや改修工事による建材混在リスク、さらに違法建材や在庫品が使われていたケースも報告されています。これらを見落とさないためには、専門業者による現地調査が不可欠です。
アスベスト調査は、単なる義務対応ではなく、企業価値を守るためのリスクマネジメントの一環です。労働安全衛生法や建築基準法に基づく法令遵守はもちろんのこと、社員や施設利用者の安全確保、そして万が一の事故やトラブル防止のためにも、調査・管理体制の整備は欠かせません。
建物管理担当者の方には、調査結果を社内で確実に共有し、記録を残す体制づくりもあわせて意識していただきたいところです。今後、解体や改修工事を予定している場合は特に、早め早めのアクションがリスクを最小限に抑える鍵となります。